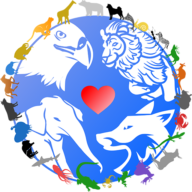オカヤドカリ
オカヤドカリ
オカヤドカリ
皆さんは「オカヤドカリ」という生き物を知っていますか?名前の通りヤドカリの仲間ですが、ヤドカリとは住んでいる場所が違っているんです。ペットとしても人気のオカヤドカリがどこに住んでいるのか、どんな暮らしをしているのかを紹介していきます!
オカヤドカリ 基本情報

〜基本情報〜
軟甲綱(なんこうこう、またはエビ綱)十脚目(じっきゃくもく、またはエビ目)オカヤドカリ科オカヤドカリ属 大きさ:3〜6cm オカヤドカリは台湾より南のインドや西太平洋など、広い地域に住んでいます。日本にも住んでいて、鹿児島県より南の南西諸島や小笠原諸島で、九州南部や四国南部にも住んでいる種類がいます。 オカヤドカリはヤドカリの仲間なので、基本的にはヤドカリと変わらず、巻貝や貝殻に体を入れて生活しています。貝殻から出ている前足や頭の部分は硬くなっていて、貝殻に守られているお腹や体の部分は柔らかくなっています。十脚目(じっきゃくもく)なので、足は10本あり、貝殻の外に出ているのは6本、中にあるのが4本です。頭に1番近いハサミがついている2本の脚は、ご飯を食べるときや喧嘩をするときに使っていて大きさが左右で違います。貝殻から出ている残りの4本の脚で歩き、中にある2本の脚で貝殻を支えているんです。他のヤドカリよりもハサミも脚も太くて頑丈なので、力持ちなんですよ。 そして、オカヤドカリがヤドカリと違う点が、住んでいる場所です。ヤドカリは水の中で生活していますが、オカヤドカリは陸で生活しているんです。オカヤドカリは元々、水の中で生活していたヤドカリが陸に上がり生活し始めたことが始まりなのだそうです。ですので、その名残で肺呼吸ではなくエラ呼吸をしているんです。 オカヤドカリは15種類いるので体の色もそれぞれです。オリーブ色や紫色、白色、赤色などで、アフリカマイマイの殻やサザエの殻など、好きな貝殻も違ってきます。同じ種類でも色や形など好きな貝殻が違ってくるのかもしれませんね。
オカヤドカリ Q&A

オカヤドカリの名前の由来は?
オカヤドカリの名前の由来の前に、ヤドカリの名前の由来は知っていますか?ヤドカリは漢字で「宿借り」と書きます。この漢字の通り、主のいなくなった貝殻を借りて住むことからこの名前が付けられたそうです。そのヤドカリの仲間であるオカヤドカリは、水ではなく陸、つまり丘に住むことから「オカヤドカリ」という名前になったそうです。 ちなみに「ナキオカヤドカリ」という種類は、貝殻の内側をひっかいて音を出すことから、鳴いているとして、ナキオカヤドカリと名前が付けられたそうです。

オカヤドカリはどうしてそこに住んでいるの?
オカヤドカリは暖かく湿った地域に住んでいて、水の中には住んでいませんが、海の近くの林で生活しています。夜に活動する夜行性と言われていて、昼間は倒れ技の下や木の根本、岩の隙間や穴などで休んでいます。ただ、夜になったから行動し出すというわけではなく、潮の満ち引きで行動しているのですが、結果的に夜に砂浜に出ることが多いというだけなんです。 先ほどもお話ししましたが、オカヤドカリは陸で生活していると言っても肺呼吸ではなく、エラ呼吸です。なので、海に近い場所に住んで乾燥しないようにしています。どうやって陸でエラ呼吸をしているのでしょうか。 オカヤドカリは貝殻の中に水を溜めて、エラ呼吸しているんです。しかもエラだけではなく皮膚でも呼吸しているので、軟かいお腹を乾燥させないように湿らせておいて、そのお腹の皮膚で呼吸しているんです。エラやお腹が乾いてしまうと死んでしまうので、定期的に水を入れ替えたり水分補給する必要があるんです。だから海の近い場所に住んでいるんですね。 オカヤドカリは暖かい地域が好きで、寒さにはとても弱いです。なので冬でも気温が低くなりすぎない場所に多くいますが、気温が15度を下回ってしまうと、地中に潜ったり冬眠して冬を越します。ただ、冬眠が長くなってしまうとそのまま死んでしまうので、やはり暖かい地域に住んでいる方が安全かもしれませんね。 オカヤドカリは家の貝殻を定期的に変えます。いわゆる引越しですね。体が大きくなるにつれて貝殻を変えていきます。オカヤドカリは脱皮をして成長していくのですが、脱皮をするときは普段より多めに水分をとってから、貝殻から出て、砂の中に潜り脱皮していきます。成長した体に合う貝殻を見つけて家にするのですが、前と全く同じ形の貝殻を探すのはとても困難です。そのときにはその新しい貝殻に合わせるように脱皮の時に体の形を変えることもできるんです。怪我やトラブルで無くなってしまった脚なども、脱皮の時に再生できるんです。魔法みたいですね。 前の貝殻は食べて栄養にしていきます。脱皮したての時は体が柔らかいので、貝殻から出ている部分を硬くするために、1週間ほどじっとして硬くなるまで待っています。お世話になった貝殻も無駄にはしないんですね。

オカヤドカリは何を食べているの?
オカヤドカリは落ち葉や木の実、フルーツ、死んだ魚介類などなんでも食べる雑食ですが、どちらかというとお肉よりも落ち葉などの植物の方が好きです。海岸の近くの林などでは落ち葉がたくさん落ちてくるので、それらを拾って食べています。ただ、オカヤドカリは脚が大きくて強いので、木に登って新鮮な葉っぱを食べることもできるんです。 ただ。葉っぱばかりを食べていては栄養が偏ってしまいます。肉を食べる時には、砂浜に打ち上げられた魚を食べるんです。海岸にあるのは死んだ魚だけではありません。私たち人間が捨てていった残飯や、打ち上げられたゴミもオカヤドカリは食べてくれているんです。ただ、人間が捨てていったゴミはオカヤドカリにとって良い栄養というわけではありません。なんでも食べることができるので食べていますが、栄養的には良くも悪くもないんです。 こうやって食事で砂浜をきれいにしてくれることから「浜辺の掃除屋」と呼ばれているそうです。オカヤドカリの手をわずらわせてしまわないように、海にゴミを捨てたり残していくのはやめましょうね。

オカヤドカリの赤ちゃんは海で生活しているの?
オカヤドカリは陸で生活していますが、赤ちゃんの時はみんな海の中で生きているんです。 繁殖期(はんしょくき)は5〜8月で、お母さんは卵を貝殻の中に産みます。赤ちゃんは貝殻の中で卵から産まれると、お母さんはすぐに海に向かいます。波打ち際まで行くと、産まれたばかりの赤ちゃんを海に放すんです。少しかわいそうですが、赤ちゃんは海の中でしか生きられないので、これも愛情なのかもしれないですね。 卵から産まれたばかりの赤ちゃんは「ゾエア」と呼ばれ、海の中でプランクトン食べながら成長していきます。約1ヶ月をかけて何度か脱皮をしていくと、「グラウコトエ(またはメガロパ)」と呼ばれる形態に成長します。ゾエアが赤ちゃんならグラウコトエは子どもという感じでしょうか。ここからもう一度脱皮をすると体はまだ小さいですが、大人と同じ体の形になります。そうすると陸で生活するために好きな貝殻を選び、陸に上がって生活するようになるんです。 その後も定期的に脱皮を繰り返して大人になっていきます。まだ小さい頃は頻繁に脱皮をしてどんどん体を大きくしていきます。大人になっても回数は減りますが脱皮をし続けます。 オカヤドカリの寿命は10〜30年以上と言われているので、長く生きているものほど、体が大きくなっているんです。 一生の中だと陸に住んでいる時間の方が長いですが、海で暮らす経験もしているので、臨機応変に対応できて長生きできるのかもしれないですね。

オカヤドカリは天然記念物なの?
オカヤドカリは世界に15種類いますが、そのうち7種類が日本にいます。その7種類が日本の天然記念物に指定されています。 1970年、小笠原諸島に住んでいるオカヤドカリの数が少なくなり、天然記念物に指定されました。ただ数が少なくなったからというよりは、オカヤドカリが本州では珍しかったからなのではないかとも言われています。沖縄ではオカヤドカリは珍しくなく、どこにでもいる生き物でした。なので沖縄では釣りをする時のエサなどにも使われていたので、オカヤドカリを捕獲(ほかく)する専門業者もいたんです。その頃は年間30トンものオカヤドカリが捕獲(ほかく)されていたそうです。ただ、その仕事を禁止するほど数が少なくなっているわけではないので、一部の場所と指定の業者、そして捕獲(ほかく)する量を限定して認められることになりました。 なので、その業者を通じて売られているオカヤドカリを買うことは違法ではありません。ですが、許可がない人間が砂浜でオカヤドカリを捕獲(ほかく)することは法律違反になるのでお気をつけください。
_shell_giant_east_african_snail_(archachatina_marginata)_principe_optimized.webp?alt=media)
オカヤドカリは絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)に指定されているの?
オカヤドカリは天然記念物に指定されているだけではなく、絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)に指定されている種類もいるんです。その種類と絶滅危惧(ぜつめつきぐ)のレベルを紹介します。 ・サキシマオカヤドカリ:絶滅危惧(ぜつめつきぐ)Ⅱ類 ・オオナキオカヤドカリ:準絶滅危惧(じゅんぜつめつきぐ) ・コムラサキオカヤドカリ:準絶滅危惧(じゅんぜつめつきぐ) これらの種類の数が減ってしまった原因としては、土地開発などによって住む場所が減ってきたり、自然の環境が悪くなってきたりしたと言われています。 ただ、特定の業者が捕獲(ほかく)することや、その業者を通して売ることは許可されています。捕獲(ほかく)したものは釣りのエサやペットとして市場に出回ります。ただ、許可されていない者が違法に捕獲(ほかく)し売っていることもあるそうなんです。 先ほどもお話ししたように昔は、年間30トンも捕獲(ほかく)されていましたが、今では専門業者だけが捕獲(ほかく)して、年間約3500kgまでに減っています。これでも多いので組合では、オカヤドカリを保護するために取り決めもされています。捕獲(ほかく)する量を年間50kgずつ減らす、繁殖期(はんしょくき)は捕獲(ほかく)しないなど決められているそうです。他にも、この仕事は受け継がないことになっていて、一代限りで終わりと決められているんです。 このように許可された業者は、ただ捕獲(ほかく)するためではなく、オカヤドカリを守るためにも決められたルールを守っているんです。 そんな中で、生活のため、無料で飼うためなど、自分たちのためだけに違法に捕獲(ほかく)する人たちもいるんです。ただ、違法に捕獲(ほかく)されたものと合法に捕獲(ほかく)されたものとを分ける法律はないので、市場に出回ってしまうとわからなくなるんです。 オカヤドカリの数を減らしてしまわないようにするためにも、ペットとして迎え入れる場合には、きちんと調べて買う必要がありますね。

オカヤドカリはペットとして飼えるの?
先ほどもお話ししたように、オカヤドカリの捕獲(ほかく)を、許可された業者を通して売られたものであれば、飼うことができます。 どのように飼育するのかを紹介していきますね。 まずはオカヤドカリのケースです。力が強いのでアクリルのものよりのガラスの水槽がいいと思われます。フタも軽々と持ち上げることができるのでしっかりと閉まり、上に重しを乗せて開けられないようにした方がいいです。 ケースが透明なままだと、壁だと認識することができずにぶつかってしまうので前に向いている面以外はバックスクリーンをつけてあげるといいと思います。 大きさは30cmぐらいのもので大丈夫です。同じ水槽で何匹か飼う場合は、小さいものなら30cmの水槽で4〜5匹、中くらいのものなら60cmの水槽で4〜5匹ほどです。 脱皮をする時などに砂の中に潜るので、砂を敷いてあげます。砂の粒は潜りやすいように1〜2mmくらいの大きさにして、敷く量は最低でも15cmの厚さが必要になってきます。敷いた砂は常に真水で湿らせておきます。その方が潜りやすく、湿度も保たれるからです。ただ砂を濡らしすぎると砂の中に酸素が回らなくなり菌が発生してしまうので注意してください。砂は数ヶ月に1回のペースできれいに洗ってあげます。水道水でよく洗った後に天日干ししてから、水で湿らせて戻してあげます。 オカヤドカリを飼う上で1番重要なのは、温度と湿度管理です。温度は20〜30度、湿度は60〜70%に保ってあげます。低温には弱いので冬にはパネルヒーターや保温カバーなどを使って温度を保ってあげてください。ただ、30度を超える温度がずっと続くと命の危険があるので温度の上がりすぎにも注意しましょう。 呼吸のためにエラやお腹を湿らせておく必要があるので、水入れは貝殻が浸かるくらい深さのあるもので、真水用と海水用の2つ用意します。真水は水分補給に、海水はミネラルを補給する時に必要なので、どちらも用意してあげてください。砂が入ってお水が汚れてしまうので、汚れたらすぐに取り替えてあげてください。 オカヤドカリはとても臆病な性格をしています。身を隠すスペースがないとストレスになってしまうので、流木やシェルター、アクセサリーなどを置いてあげると良いです。 大事な貝殻は何個か用意してあげる必要があります。気に入ったものにしか住まないので、お気に入りを見つけられるようにいろんなタイプのものを用意してあげるといいかもしれません。水槽に何匹か飼っていると、他の子の貝殻を奪うこともあるそうなので、喧嘩しないようにたくさん用意してあげましょう。 エサは雑食なのでいろんなものを食べます。果物、野菜、海藻、魚の切り身などバランスよく与えてあげます。飼い主とオカヤドカリが同じ食材で食事する時があるかもしれませんね。ただ、辛いものや匂いの強いものは嫌うことがあるので注意してください。 オカヤドカリは人に懐くようなタイプではありませんが、寿命が長いので、長く一緒に過ごすことができるかもしれません。大切に育てて、一緒にいられる時間を大切にしていきたいですね。

あなたも『動物完全大百科』の一員になりませんか?
あなたの知識をQAにして、全世界に発信しましょう。 ※掲載は購入後に有効となります。 さあ、私たちと一緒に情報を共有しましょう!
オカヤドカリ 種類

・オオナキオカヤドカリ ・オカヤドカリ ・コムラサキオカヤドカリ ・ナキオカヤドカリ ・ムラサキオカヤドカリ ・オオトゲオカヤドカリ など
コメントしませんか?
おめでとうございます! あなたが初めてのコメンテーターです!

あなたの“好き”リストを作ろう!
オカヤドカリ
気になる動物をお気に入りに登録!後からすぐに見返せる、あなただけのリストを作りましょう。

コメントしませんか?
※ご注意:記事内に掲載するコメント権の購入になります。
あなたの好きを見つけよう!
当ショップでは、様々な動物をテーマにしたユニークで魅力的なグッズを取り揃えております。
オカヤドカリ 参考文献
オカヤドカリ 使用メディア紹介

出典:https://pixabay.com/ja/photos/ヤドカリ-甲殻類-隠者-カニ-1759943/

出典:https://pixabay.com/ja/photos/オカヤドカリ-隠者-カニ-3576536/

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ヤドカリ2602.jpg

出典:https://pixabay.com/ja/photos/カニ-ヤドカリ-陸上動物-砂浜-1807903/

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermit_crab_4.jpg

動物完全大百科をあなたのメディアで豊かにしよう!
動物完全大百科では、動物の素晴らしい写真や動画を常に募集しています。もしあなたが共有したいメディアがあれば、ぜひご提供ください。あなたの投稿はクレジット付きで動物完全大百科に掲載され、多くの動物愛好家に届けられます。動物の魅力と多様性を一緒に伝えましょう。