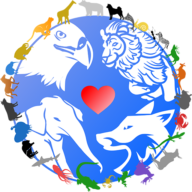モズ
モズ
モズ
皆さんは「モズ」という鳥を知っていますか?身近な鳥なので見たことのある方や鳴き声を聞いたことのある方はいるかもしれませんが、都会ではあまり見かけない鳥になってきました。モズの習性や鳴き声は少し変わっていて特徴があります。そこも含めてモズを紹介していきます。
モズ 基本情報

鳥綱(ちょうこう)スズメ目モズ科モズ属 全長:19〜20cm モズは中国東部から南部、朝鮮半島、ロシア南東部、ウスリー南部、樺太、そして日本にも住んでいます。日本では全国で見られる鳥です。海外の寒い地域では冬を越すために渡りをしますが、日本ではほとんどが1年中同じ場所に住む留鳥(りゅうちょう)です。ただ、北海道や東北の寒い場所に住んでいるモズは冬に暖かい場所へ、沖縄に住んでいるモズは夏に涼しい場所に移動します。季節によってちょうどいい気温の場所に移動しているんですね。 モズは小さい体の割には頭が大きく、背中は青みがかったグレーでお腹は茶色、体の横はオレンジ色をしています。オスは頭もオレンジ色をしていて、目の周りに黒く太い線が入っています。メスは頭が茶色く、目の周りに黒い線は入っていません。細長い尻尾を持っていて、木に止まっている時などにクルクルと円を描くように回しています。 なんといっても小さい体と可愛らしい顔からは想像できない、太く先が曲がり尖ったくちばしを持っています。タカと同じようなくちばしで、可愛らしいなと思って近づくのは危険ですね。
モズ Q&A

モズの名前の由来は?
モズは漢字で「百舌」や「百舌鳥」と書きます。モズは様々な鳴き声を出し、時には他の鳥や動物の鳴き声を真似て鳴いたりします。このことから「百の舌を持つ鳥」として百舌鳥という漢字になりました。 「百」という漢字は「もも」とも読めるのでモズの「モ」に当てはまりそうですが、「舌」を「ズ」と読んでいるのでしょうか。 鳥の名前にある「ズ」や「ス」は鳥の接尾後として使われることがあります。「カラス」もその一つです。なのでモズの「ズ」は鳥を表していると言われています。 元々は百舌という漢字でモズと読んでいたそうですが、これだけだと何を表しているのかわからないということになり、鳥をつけたそうです。 漢字にもなるほど、いろんな声を出すことができるんですね。 ちなみに他の漢字で「鵙」と書きます。左の貝という漢字は、犬が目をキョロキョロさせていることを表していて、目をキョロキョロさせて獲物(えもの)を獲る鳥なのでこの漢字になったそうです。ただ獲物(えもの)を獲る時は、ほとんどの動物が目をキョロキョロさせている気がするのでこの漢字だけでモズと読むのは特別な感じがしますね。

モズはどうしてそこに住んでいるの?
モズは緑の多い林や、草原、農耕地、河辺、河川敷、住宅地などに住んでいますが、どこも開けた場所にいます。 繁殖期(はんしょくき)は夫婦や家族で生活していますが、それ以外の時期は1人で過ごしています。 秋には自分のなわばりを示すときに出す「高鳴き」と呼ばれるもので争い、自分のなわばりを確保します。冬に快適に過ごすためなのかもしれませんね。 モズを住宅地で見られる地域もありますが、都心の方は開けた場所がなかったりエサが少なくなってしまうので、見られなくなってしまっていますね。

モズは何を食べているの?
最初の方にもお話ししましたが、モズはくちばしがタカのように鋭くなっています。そのくちばしで虫やクモ、ガ、ハチ、ミミズ、トカゲなどの小さいものから、自分より大きなモグラやネズミ、スズメなどの小鳥も捕らえてしまう動物食なんです。小さくて可愛らしいですが、タカと同じくちばしを持っているので、小鳥界ではとても強いのかもしれませんね。 モズは木の上などの高いところから獲物(えもの)を探して、見つけたら飛んでとりにいき、また木の上に戻ってから食べるというエサのとりかたをします。 モズは他にも変わったことをします。それは「モズの早贄(はやにえ)」です。モズはとった獲物(えもの)を生垣の尖ったところや、有刺鉄線の尖った部分などに刺してそのままにするのです。その光景が生け贄(いけにえ)として神様に捧げていると言われていたことから「モズの早贄(はやにえ)」と呼ばれるようになりました。 これを知らずに初めて見てしまうと、ゾッとする光景ですね。

モズはどうやって増えるの?
モズは2〜8月が繁殖期(はんしょくき)で、他の鳥よりも少し早くから繁殖(はんしょく)し始めます。 「モズの名前の由来は?」でもお話しした通り、いろんな声を出しますが、それはメスへのアピールです。無事にカップルが成立すると、オスとメスで一緒に巣を作ります。木の上や茂みなどに木の枝を組み合わせて巣を作ったら、そこに4〜6個の卵を産みます。メスが卵を温めるのですが、そこにはなんと違う鳥の卵があったりするんです。どういうことなのでしょうか。 「カッコウ」という鳥が犯人なのですが、カッコウは自分で巣は作らずに、他の鳥の巣に産んで温めて育ててもらうんです。その預け先の一つがモズの巣なのです。モズは気づいているのか気づいていないのかわかりませんが、自分が産んだ卵と同じように温め、育てるのです。 14〜16日間温め、無事にヒナが産まれると約14日間で巣立ちします。ただ自然の中は何があるかわかりません。産む卵の数は多いですが、地域によってはキツネやヘビ、カラスなどの天敵もいて卵から産まれる前に食べられてしまうこともあります。 立派なくちばしを持っているとはいっても体は小さいので、天敵は多くなってしまうのかもしれませんね。

モズの高鳴きって何?
「モズはどうしてそこに住んでいるの?」でもお話ししましたが、モズは「高鳴き」と呼ばれるものを秋から11月ごろにかけて行います。 この高鳴きはなわばり争いのときに出すもので、「キチキチキチ」「ギチギチギチ」「ジュンジュン」「ギュンギュン」「キーィキーィ」「キーキー」「キリキリキリ」などの甲高い声を出します。この鳴き声で自分のなわばりを確保しているんです。モズが食べているのは動物で、冬になると動物は冬眠などで少なくなってしまいますよね。そのエサが少なくなる冬を過ごすためには、自分のなわばりをきちんと確保して他のモズにエサを取られないようにしているんです。モズは繁殖期(はんしょくき)以外は単独で行動しているので、この高鳴きはオスだけではなくメスも鳴いて争います。例え、共に繁殖期(はんしょくき)を過ごした相手や自分の子どもであっても、自分のなわばりに入ってきたら高鳴きですぐに追い出してしまうんです。 この高鳴きは「モズの高鳴き七十五日」と言われていて、モズの高鳴きを聞いて75日目に霜が降ると言われているんです。なので農作業をする方たちは、この鳴き声を聞いて次の作業の目安にしていることもあるのだそうです。 モズは1人で生きていくためにオスやメス、子どもも関係なく戦っているんですね。

モズはモノマネができるの?
モズは先ほどもお話しした通り、繁殖期(はんしょくき)はメスに気に入られるために、オスがさえずりをするのですが、その鳴き声は他の鳥を真似しているんです。メスが気にいるポイントは、複雑にいろんなパターンの鳴き方をしている、というところです。なのでオスはメジロやヒヨドリ、ホトトギス、ウグイス、カッコウなどの鳥の声や、馬の「ヒヒ〜ン」という声までも組み合わせて鳴くんです。短い音を組み合わせて鳴くのですが、その数がすごいんです。平均して1秒間に7種類もの鳴き声を出していて、多いモズではなんと1秒間に10種類というので驚きです。そんなにいろんな音を出すと、逆になんの動物の鳴き声を真似しているのかわからなくなりそうですよね。 ただ、やはり1秒間に10種類を組み合わせて鳴いているオスの方がすぐに気に入られるので、モノマネが上手くて早くできるオスがモテるんでしょうね。

モズの早贄(はやにえ)って何?
先ほどもお話ししましたが、モズはとった獲物(えもの)を生垣や有刺鉄線の尖ったところに刺しておく習性があります。これはただの儀式なのでしょうか。 モズの早贄(はやにえ)は儀式ではなく、ちゃんとした理由があるんです。 早贄(はやにえ)は秋から冬にかけて増えていきます。これは高鳴きをする理由と似ているのですが、冬はエサとなる動物たちが冬眠をして減ってしまいます。なので、備蓄(びちく)のために刺して干しておくのだそうです。備蓄(びちく)をしてまで栄養を蓄えておかなければいけないのも理由があります。これは先ほどの、さえずりモノマネに繋がっていくのですが、さえずりの数が多く出せるということはそれだけ元気で健康だということです。なので、子孫を残すために健康でなくてはならない、ということは厳しい冬の間でも栄養が取れるようにしておかなければならない、ということになるのです。 モズの早贄(はやにえ)には他にも理由はありますが、きちんとした検証はされておらず、説にとどまっているものもあります。 まずはエサを食べやすいようにしているという説です。モズは足の筋肉が弱く、足で掴んだまま食べるのが難しいので、刺すことによってくちばしを使うだけで食べられるからと考えられています。 他には本能で捕まえてしまうという説もあります。とにかくエサを見つけると捕まえてしまい、とりあえず刺しておくけど、満腹の場合は食べないという説です。 他にもなわばりを示すためなどの理由もありますが、今のところ備蓄(びちく)しているというのが、検証されたものなので有力なのかもしれません。 モズの早贄(はやにえ)が儀式だと怖かったですが、生きるため、子孫を残していくために必要なことだったとわかると少し安心しますね。

モズは絵や言葉になっているって本当?
モズは鳴き声に特徴があり、よく見られることから昔から人間に親しまれてきた鳥です。そのため絵や逸話、言葉になっています。 1番有名な絵は、宮本武蔵の古木鳴鵙図(こぼくめいげきず)です。一本の木の先にモズが描かれています。 大阪府堺市にある大仙陵古墳のある場所は「百舌鳥耳原(もずのみみはら)」という地名がつけられています。その昔、仁徳天皇(にんとくてんのう)がこの地に自分のお墓を作っていたところ、森からシカが現れ襲われそうになりました。ですがその寸前で、シカが死んでしまったのです。その死んだシカの耳からモズが現れました。モズがシカから守ってくれたとして、この地にモズの名前を入れたのだそうです。この逸話からモズは堺市の鳥に指定されていて、「もずやん」「モッピー」というモズをモチーフとしたキャラクターがいるんだそうです。 他にも「百舌勘定(もずかんじょう)」という言葉を聞いたことがありますか?この言葉は昔話からきていて、モズがシギとハトと十五文の買い物をしました。するとモズは「シギは「シ」から始まるから七文(しちもん)出して、ハトは「ハ」から始まるから八文(はちもん)出せばいいよ」と言いくるめて自分はお金を出しませんでした。モズは喋りが上手く言いくるめることができたというお話です。この昔話から、自分はお金を出さずに他の人に払わせることを「百舌勘定」というのです。モズの言いくるめかたも無理やりな気もしますが、いろんな声を出していることを喋りが上手いとするのは面白いですね。 キャラクターや面白い話がある反面、モズの早贄(はやにえ)から怖い象徴のようなものになっていることもあります。 江戸時代は、モズが鳴く夜には死人が出ると言われていたり、ドイツでは「絞め殺す天使」、イギリスでは「屠殺人(とさつじん)の鳥」と言われています。屠殺(とさつ)は家畜を殺すという意味ですが人がついているので家畜のように人を殺す鳥と恐れられていることがわかりますね。 怖い面も良い面もどちらもありますが、昔から人間の近くで暮らしてきたことがわかりますね。
_optimized.webp?alt=media)
モズは絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)に指定されているの?
モズは全体をみると絶滅(ぜつめつ)の恐れは低いとされていますが、地域によっては数が少なくなっているところがあります。 特に都心では数が減っていて、東京23区と北多摩は絶滅危惧II類(ぜつめつきぐにるい)に、南多摩と北多摩は純絶滅危惧(じゅんぜつめつきぐ)に指定されていて、神奈川県では減少種に指定されています。指定されている名前はそれぞれ違いますが、どれも数が少なっていて絶滅(ぜつめつ)に近づいているという意味があるので、自然を守りエサとなる動物が戻って、モズも戻ってきてくれるのを願うばかりですね。 他の地域や種類も指定を受けています。 ・アカモズ:絶滅危惧(ぜつめつきぐ) ・シマアカモズ:熊本県で要注目種、鹿児島県で分布特性上重要 ・チゴモズ:絶滅寸前(ぜつめつすんぜん) いろんな地域で、モズが快適に過ごせるようになると良いですね。

あなたも『動物完全大百科』の一員になりませんか?
あなたの知識をQAにして、全世界に発信しましょう。 ※掲載は購入後に有効となります。 さあ、私たちと一緒に情報を共有しましょう!
モズ 種類

・チゴモズ ・カタジロチゴモズ ・モズ ・アカモズ ・セアカモズ ・アカオモズ ・ハイガシラモズ ・アフリカセアカモズ ・クロビタイセアカモズ ・タカサゴモズ ・チベットモズ ・フィリピンモズ ・ハグロカタシロモズ ・ヒメオオモズ ・アメリカオオモズ ・オオモズ ・ミナミオオモズ ・オオカラモズ ・ハグロオナガモズ ・オグロオナガモズ ・ズグロオナガモズ ・オジロオナガモズ ・カタジロオナガモズ ・タンザニアオナガモズ ・サントメオナガモズ ・ズアカモズ ・シロクロモズ ・シマアカモズ
コメントしませんか?
おめでとうございます! あなたが初めてのコメンテーターです!

あなたの“好き”リストを作ろう!
モズ
気になる動物をお気に入りに登録!後からすぐに見返せる、あなただけのリストを作りましょう。

コメントしませんか?
※ご注意:記事内に掲載するコメント権の購入になります。
あなたの好きを見つけよう!
当ショップでは、様々な動物をテーマにしたユニークで魅力的なグッズを取り揃えております。
モズ 参考文献
モズ 使用メディア紹介

出典:https://www.pexels.com/ja-jp/photo/15346186/

出典:https://pixabay.com/ja/photos/野生動物-鳥-自然-屋外で-3262980/

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lanius_bucephalus.JPG

出典:https://pixabay.com/ja/photos/鳥-モズ-動物-野生動物-6921636/

出典:https://pixabay.com/ja/photos/鳥-モズ-鳥類学-種族-6900923/

その他
出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tadeiyama_Kofun_haisho.JPG

出典:https://pixabay.com/ja/photos/鳥-モズ-動物-野生動物-6921634/

動物完全大百科をあなたのメディアで豊かにしよう!
動物完全大百科では、動物の素晴らしい写真や動画を常に募集しています。もしあなたが共有したいメディアがあれば、ぜひご提供ください。あなたの投稿はクレジット付きで動物完全大百科に掲載され、多くの動物愛好家に届けられます。動物の魅力と多様性を一緒に伝えましょう。
















_optimized.webp?alt=media)