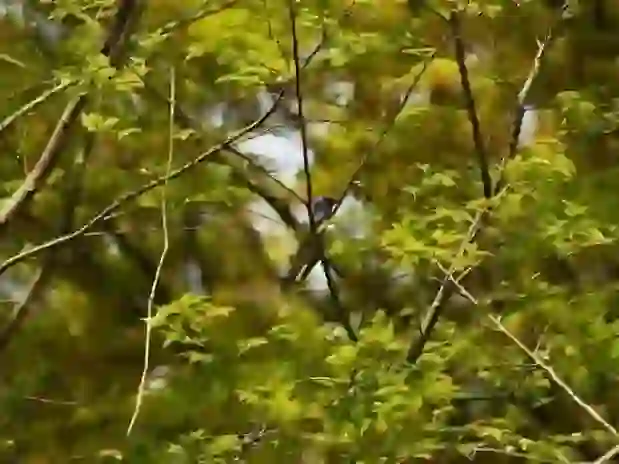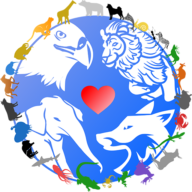オオルリ
オオルリ
オオルリ
オオルリという綺麗な瑠璃色(るりいろ)の鳥を知っていますか? その美しい姿から「幸せの青い鳥」と呼ばれ、さえずりも美しくフルートに例えられるほどです。 そんな美しいオオルリのことをもっと詳しく紹介していきます。
オオルリ 基本情報

鳥綱(ちょうこう)スズメ目ヒタキ科オオルリ属
全長:16〜17cm
翼開長(よくかいちょう):約27cm
体重:20〜26g
オオルリは中国東北部や朝鮮半島、日本で繁殖し、インドネシア、フィリピンなど東南アジアで冬を越します。日本では夏鳥とされていて、ほぼ日本全国で見ることができます。
スズメより少し大きいその体は、頭から背中、尾にかけてまで鮮やかな青色、いや、オオルリに似合う色の名前は瑠璃色(るりいろ)ですね。お腹は白く、綺麗なコントラストです。ですが、その綺麗な瑠璃色(るりいろ)はオスだけで、メスの背中は茶色い羽をしています。
オオルリの瑠璃色(るりいろ)は、「瑠璃三鳥(るりさんちょう)」と呼ばれる代表的な青い鳥の一つで、他にコルリ、ルビタキという鳥がいます。
最初にもお話ししましたが、オオルリが美しいのはその姿だけではなく、さえずりもとても美しいのです。
「ピールーリー」や「ピーリッ、ポピーリポピーリ、ジジーッ」、「ピーリリリィリィ、チリチリッ」と伸びやかにゆっくりと鳴きます。その声はまるでフルートのように美しく、初夏の森を彩ってくれます。
文字ではその美しさが伝えられないのですが、オオルリのさえずりも「日本三鳴鳥(にほんさんめいちょう)」のひとつとされていて、他にウグイスとコマドリという鳥がいます。
姿も声も、日本を代表する美しい鳥とされているんですね。
オオルリ Q&A

オオルリの名前の由来は?
もうみなさん、名前の由来は予想がついているのではないでしょうか。
そうです。光沢のある瑠璃色(るりいろ)をしていることからその名が付けられました。
室町時代には「るりてう(瑠璃鳥)」と呼ばれ、安土桃山時代には「るり(瑠璃)」と呼ばれていました。ただ、コルリという別の鳥のことも同じように呼んでいたため、江戸中期にオオルリとコルリを区別するために今の名前になったそうです。
大きい瑠璃色(るりいろ)の鳥をオオルリ、少し小さい瑠璃色(るりいろ)の鳥をコルリ。なんだか安易な名前で区別されてしまったような気がしますね。

オオルリはどうしてそこに住んでいるの?
オオルリは低い山から少し高い山の山地や、熱帯雨林(ねったいうりん)などの川のそばで暮らしています。繁殖(はんしょく)の時は岩壁や土壁に巣を作って卵を産みます。メスがオスのように目立つ色ではないのは、このような岩や土のスキマに巣を作るので、目立たないようにするためかもしれません。
春や秋の渡りの時期には、庭や公園などでも見られるので、運が良ければ出会えるかもしれませんね。

オオルリは何を食べているの?
川のそばにはたくさんの虫が飛んでいるのを見たことがありませんか?その飛んでいる虫がオオルリのエサとなるのです。
ですがオオルリには虫とり網などの便利な道具はありません。飛んでいる虫をどうやって捕まえているのでしょうか。
それは「フライキャッチング」と言われる方法です。枝から飛んで虫をキャッチし、また同じ場所に戻ってくる飛び方です。飛んでいる虫を見つけたら、空中で角度を変え、細い木々の隙間さえも通り抜け、虫が逃げることができないほど素早く動きます。そうして捕まえるとまた元の枝に戻ってくるのです。
飛ぶ虫が主食ですが、それ以外でも幼虫やクモ、果実なども食べています。地上に降りてエサを取ることもありますが、その動きは素早く、すぐに木の上に飛んでいきます。
目で狙いをつけておいて、すぐに元の枝に戻れるようにしているんでしょうね。

オオルリはどうやって増えるの?
オオルリのオスは、繁殖期(はんしょくき)になるとひときわ大きな声でさえずります。その声や体の色で、メスは相手を選ぶのです。メスをめぐって、オス同士でケンカをすることもあります。私のためにケンカはやめてーというドラマも起こっているかもしれませんね。ですが選ぶのはメスなので、ケンカをしてもどちらも選ばれないという悲しい結果も中にはあるかもしれないと思うと胸が痛いです。
無事に夫婦になったオオルリは巣を作ります。その場所を決めるのはオスの役目で、やわらかいコケなどを使って巣を作るのがメスの役目です。役割分担をきっちりしているんですね。
巣に卵を産むと、メスが卵を温めます。約14日間温め続けます。それほど長いわけではないですがオスにも交代して温めて欲しいと思ってしまいますね。
無事に孵化(ふか)すると、オスも子育てをしていきます。オスとメスでエサを運んでヒナに食べさせてあげます。生まれたばかりのヒナはオスとメス、どちらもメスのように茶色い羽をしています。最初から瑠璃色(るりいろ)をしているわけではないんですね。
それもそのはず。やはりヒナというのはまだ飛ぶこともできず、小さいので、身を守ることができません。メスと同じ色であれば、巣のある場所と同じ色で目立たないので、敵から見つけられにくいのです。
ヒナは12日ほどで巣立つことができますが、巣立つ前に10日間ほど家族水入らずの時間を過ごします。家族が離れて暮らす覚悟や、その前の思い出を作る時間なのかもしれませんね。
巣立つ時にはオスは瑠璃色(るりいろ)になっているのでしょうか。
あの瑠璃色(るりいろ)になるにはなんと2〜3年かかるのです。巣立ったと行ってもまだまだ半人前だぞと言われているようですね。その証拠に本当に少しだけ、半分だけ青いのです。瑠璃色(るりいろ)が一人前の証拠なのかもしれません。

オオルリはどこで見られるの?
オオルリは4月下旬ごろに日本にやってくるので、その時期が見られるタイミングかもしれません。6月ごろから繁殖(はんしょく)の時期に入りますが、なんと言っても警戒心(けいかいしん)が強くなってしまうのです。子孫を残すためなので仕方ないですよね。
なので、日本に来たばかりの頃の方がまだ警戒心(けいかいしん)が薄いので、近づくことが出来るかもしれません。
オオルリはお気に入りの場所があると、長い間その場所でさえずります。じゃあそのさえずりを頼りに見つければいいんだ!と思うかもしれませんが、その時期、同じように夏鳥がたくさん鳴いているので、聞き分けられるとどこにいるかわかるかもしれませんが、難しそうですね。
目立つ瑠璃色(るりいろ)だからそれを見つければいいんじゃないか!と思った方もいるかもしれません。ただ、オオルリは木の高いところにいるため、下から見ると白いお腹の部分しか見えないのです。青い部分が見えても木の影で黒に見えてしまい、見分けるのが難しいようです。なので、山に登って行ってその途中などで見つけるのがわかりやすいかもしれません。
幸せの青い鳥はなかなか見つけさせてくれないようですね。幸せはそんなに簡単じゃないと言っているのかもしれません。

オオルリは家で飼えるの?
オオルリはかつて、飼い鳥として人気があったそうですが、今は鳥獣保護法(ちょうじゅうほごほう)という法律で飼うことは禁じられています。
ですが、この法律を破り、違法に飼育されているのです。しかもその現場が毎年出てきているというのが驚きです。
この法律は、オオルリや他の鳥も守るための法律です。その美しい姿とさえずりに飼いたくなる気持ちもわかりますが、日本を代表する美しい鳥を守るために、地球全体で守っていきたいですね。

オオルリは絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)に指定されているの?
オオルリは他の夏鳥とともに、1980年代ごろから減少していきました。それは熱帯雨林(ねったいうりん)などの伐採(ばっさい)で、オオルリ達の住む場所が無くなったことが原因とされています。
ですがそれだけではありません。
オオルリは先ほどもお話しした通り、飼うことが禁止されているのですが、違法に飼っていることが発見されているということは、違法に捕まえているということになります。密猟されていたという記録も残っており、環境だけではなく、捕まえてしまうことも減少の原因の一つなのではないかと思います。
オオルリや他の夏鳥を守るための調査が行われているようですが、オオルリの数が増えている地域もあれば、変わらない地域もあり、あまり原因が分かってないようです。
オオルリは現在、絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)とまではいかない、準絶滅危惧種(じゅんぜつめつきぐしゅ)などに指定されていて、地域によって違うようです。オオルリが指定されているものを地域別で紹介していきます。
・千葉県
重要保護生物(じゅうようほごせいぶつ)(B)
・山形県、東京都北多摩
絶滅危惧II類(ぜつめつきぐにるい)
・東京都南多摩、西多摩、神奈川県、大阪府、和歌山県、山口県、福岡県
準絶滅危惧種(じゅんぜつめつきぐしゅ)
・茨城県、滋賀県
希少種(きしょうしゅ)
・埼玉県
地帯別危惧(ちたいべつきぐ)
・兵庫県
要注目種(ようちゅうもくしゅ)
・岡山県
留意(りゅうい)
このように日本全国でオオルリ達を守ろうとしている地域がたくさんあります。指定されることで、地域全体で守ることができるようになるのでまたオオルリがたくさん見られる日も来るかもしれませんね。
ちなみに日本で初めて繁殖(はんしょく)した動物園に送られる「繁殖賞(はんしょくしょう)」というものがあります。愛知県の豊橋総合動植物公園が1991年に自然繁殖(しぜんはんしょく)で、2003年には人工繁殖(じんこうはんしょく)でこの繁殖賞(はんしょくしょう)を受賞しています。
人間の手でオオルリが減ってしまったと言っても過言(かごん)ではありませんが、今の人間達の手によって守っていこうとされているんですね。

あなたも『動物完全大百科』の一員になりませんか?
あなたの知識をQAにして、全世界に発信しましょう。 ※掲載は購入後に有効となります。 さあ、私たちと一緒に情報を共有しましょう!
オオルリ 種類

- オオルリ
コメントしませんか?
おめでとうございます! あなたが初めてのコメンテーターです!

あなたの“好き”リストを作ろう!
オオルリ
気になる動物をお気に入りに登録!後からすぐに見返せる、あなただけのリストを作りましょう。

コメントしませんか?
※ご注意:記事内に掲載するコメント権の購入になります。
あなたの好きを見つけよう!
当ショップでは、様々な動物をテーマにしたユニークで魅力的なグッズを取り揃えております。
オオルリ 参考文献

- Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/オオルリ
- サントリーの愛鳥活動 https://www.suntory.co.jp/eco/birds/encyclopedia/detail/1397.html
- CANON BIRD BRANCH PROJECT 生物多様性の取り組み https://global.canon/ja/environment/bird-branch/photo-gallery/oruri/index.html
- NATURE LAND NOSE ネイチャーランド能瀬 https://natureland-nose.com/bird/news_bird/3999/
- GOOPASS ANIMAL MAGAZINE https://goopass.jp/animal/bird/book/oruri
- 目に見えるいきもの図鑑 https://orbis-pictus.jp/article/oruri.php
- 森と水の郷あきた あきた森づくり活動サポートセンター総合情報サイト http://www.forest-akita.jp/data/bird/26-kibi/kibi.html
- みやざき ひむか学ネット http://www.miyazaki-c.ed.jp/himukagaku/unit/taiyo_12/page3_2.html#:~:text=スズメより少し大きく、ヒタキ,鳴鳥といわれます。
- 語源由来辞典 https://gogen-yurai.jp/ooruri/
- 四国自然史科学研究 三嶺におけるオオルリCyanoptila cyanomelana(スズメ目:ヒタキ科)の個体数の年変動 https://www.jstage.jst.go.jp/article/sinh/12/0/12_6/_pdf
- 全国鳥類繁殖分布調査 ニュースレター 第6号 https://www.bird-atlas.jp/news/banews06.pdf
- 北海道中央部, 大雪山系におけるオオルリの個体数調査 https://www.ht-shizenkan.com/data/study/hts-study-25.pdf
オオルリ 使用メディア紹介

出典:https://pixabay.com/images/id-3233886/

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4G4A4641B.jpg

出典:https://pixabay.com/images/id-7172788/

出典:https://pixabay.com/images/id-4153041/

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki-c-ooruri.jpg

動物完全大百科をあなたのメディアで豊かにしよう!
動物完全大百科では、動物の素晴らしい写真や動画を常に募集しています。もしあなたが共有したいメディアがあれば、ぜひご提供ください。あなたの投稿はクレジット付きで動物完全大百科に掲載され、多くの動物愛好家に届けられます。動物の魅力と多様性を一緒に伝えましょう。